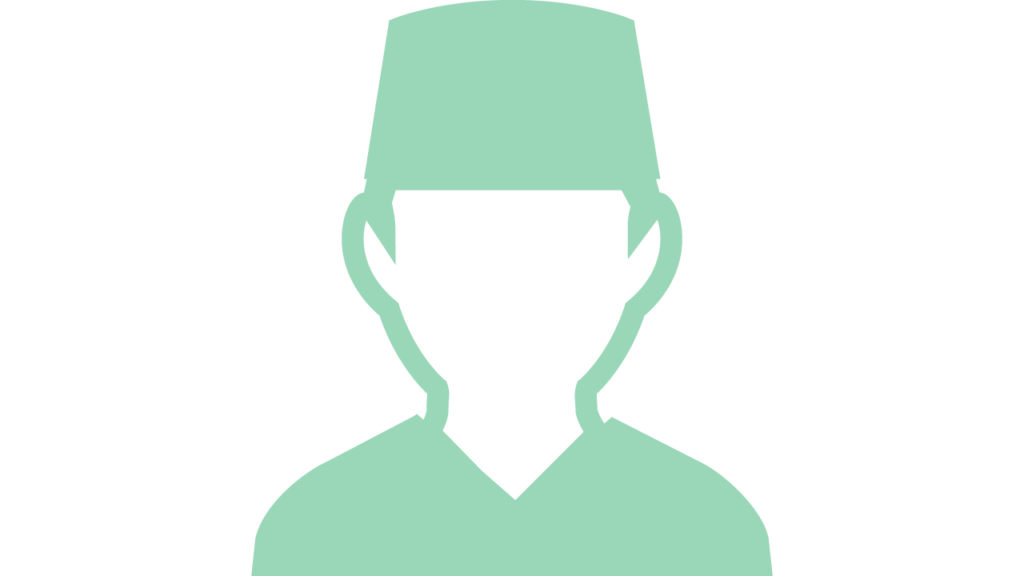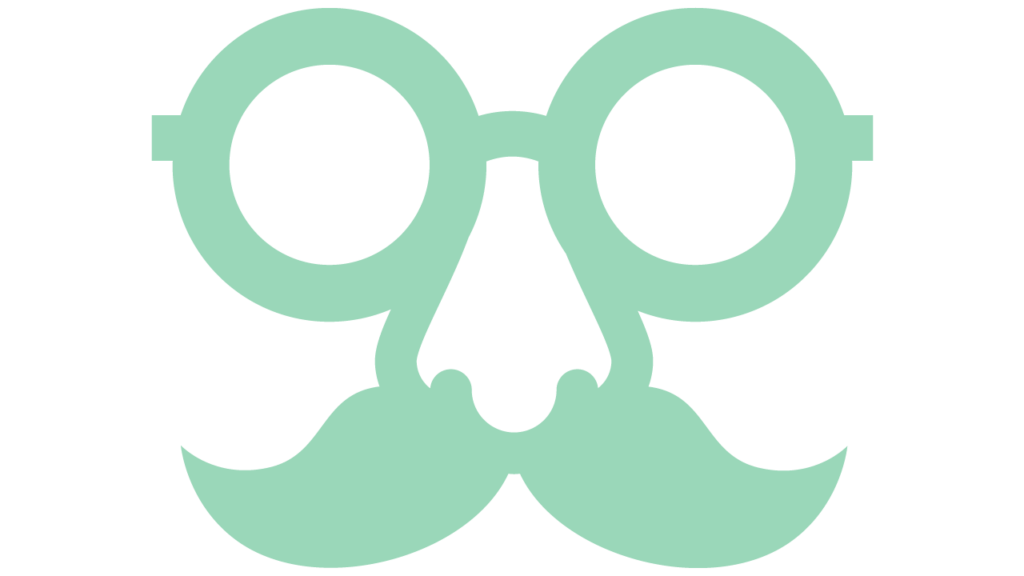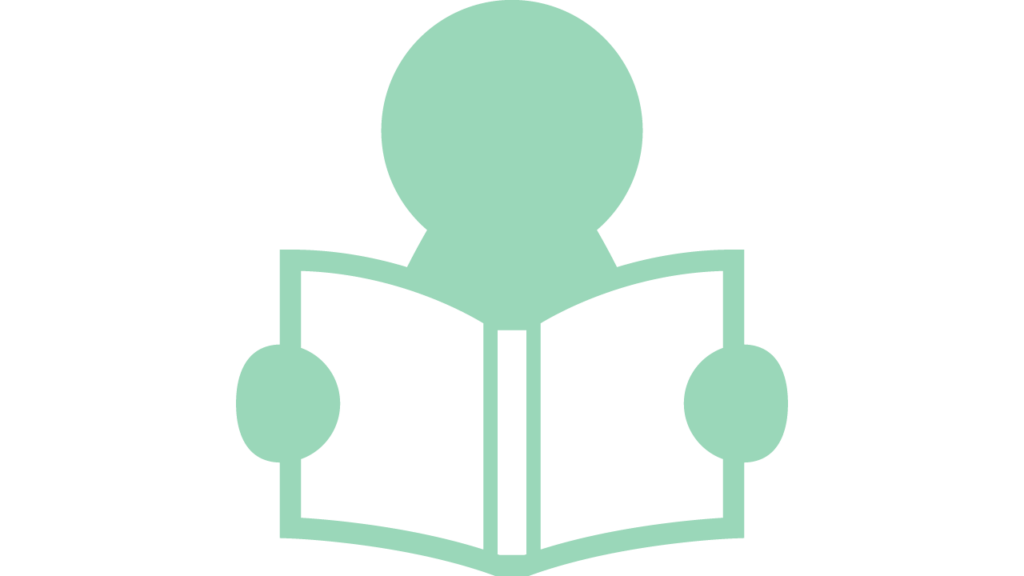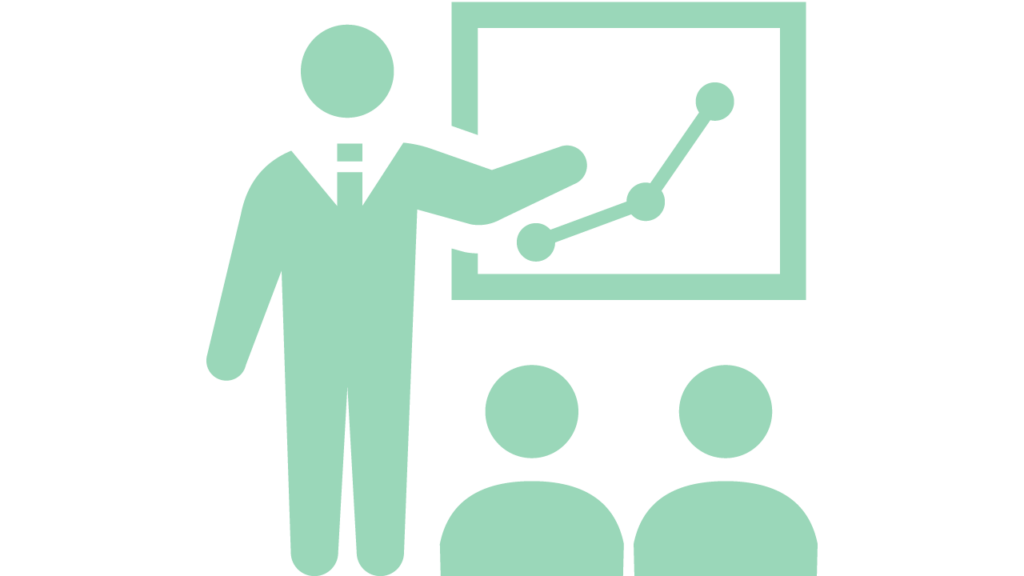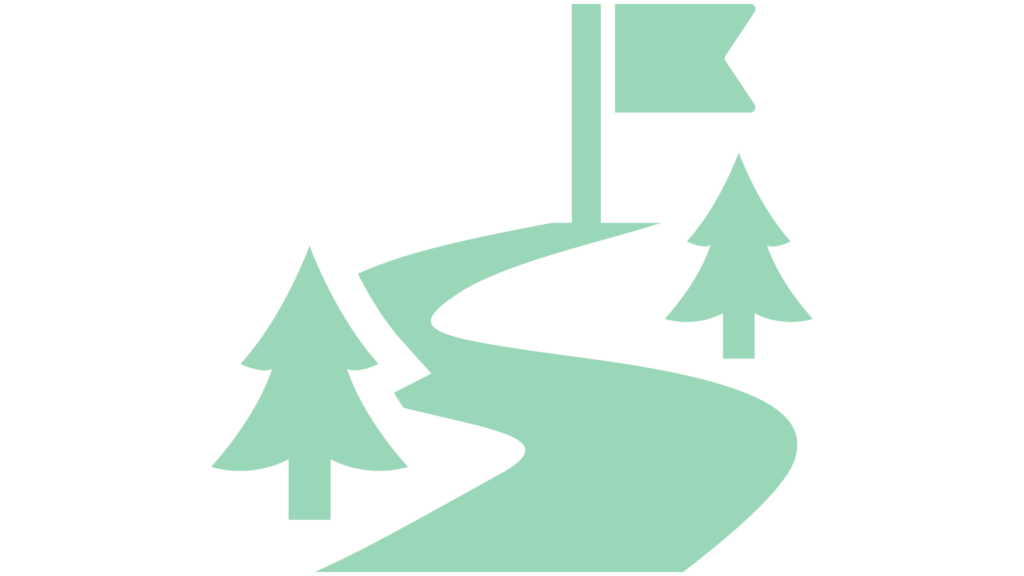帯文– tag –
-

『山の単語帳』田部井淳子
山の言葉を知らなくても、山に登ることはできます。しかし山の言葉をひとつ知れば、その分だけ山の輪郭が立ち上がってくるはずです。 山登りやハイキングを始め立てのころは、一緒に登っている仲間が使う用語がわからないことが多々あるものです。「山の専... -

『うたびとの日々』加藤治郎
歌がそこにある日々、日々から紡ぎだされる歌。 一般的には短歌を詠む人たちのことを歌人(うたびと)と呼びます。しかしもう少し深い意味において「歌人とは何か」「何のために歌を詠むのか」という問いは、単純な回答を拒否するような問いかけであるよう... -

『ジョークなしでは生きられない』阿刀田高
毎日の生活が行き詰っているという人にとって、ジョークのひとつが救いになることがあります。本書は世界のジョークから傑作ジョークを集めたコンパクトな一冊です。90の小題はどれも3ページ程度で、さまざまなジョークを取り混ぜながらの著者の文章が、ジョークの世界へ導いてくれます。 -

『はじめてのやさしい短歌のつくりかた』横山未来子
「短歌に興味はあるけれど、いったいどうやって始めればいいのだろうか?」あるいは「そもそも短歌ってどんなもの?」という疑問をもっている人にとって、本書はそのタイトルの通り最適な入門書といえるのではないでしょうか。 -

『読書からはじまる』長田弘
読書に没頭できる時間があること。それは人にとっても、本にとっても幸せなこと。 本書の表紙には「人は、読書する生き物である」という言葉が書かれています。本を読む習慣のある人にとって、読書の時間とは何ともいえない至福の時間であることでしょう。... -

『ひとは情熱がなければ生きていけない』浅田次郎
情熱を補充してみませんか? この本のタイトルを見たときに、「情熱をもって生きているのだろうか?」と自分に思わず問いかけてしまいます。「情熱」の熱量は人によってさまざまだとは思いますが、生きていく上で、少なからず「情熱」と呼ぶべきものが必要... -

『短歌を詠む科学者たち』松村由利子
そのコインの片面には「科学」と書かれています。もう片面には「短歌」と書かれています。そんな少し変わったコインを持った七人の物語。 短歌を詠むのは歌人に限りません。本書は、短歌を詠んでいた(詠んでいる)科学者たちを取り上げた一冊です。著者は... -

『天職は寝て待て ― 新しい転職・就活・キャリア論』山口周
どこで働くか、誰と働くか、いつ働くか、どう働くか。それらはすべてあなた自身が決めればいい。 「なぜあなたは今の仕事を選んだのですか?」 この問にはっきりとした回答をもっている人は、その仕事が天職なのかもしれません。しかし組織に属しながら働... -

『両手いっぱいの言葉 ― 413のアフォリズム ― 』寺山修司
ことばは時に劇薬である。特に寺山修司のことばは! 演劇、映画、詩、俳句、短歌、評論、写真など多彩な才能で知られる寺山修司。彼の残した多くの言葉がこの一冊に収められています。「愛」「美」「暴力」「文明」「変身」「飛翔」「友情」「夢」など52章... -

『言葉のゆくえ ― 俳句短歌の招待席』坪内稔典 / 永田和宏
俳句と短歌、言葉の交差点。 俳句も短歌も大きな分類においては短詩型文学という括りに入ります。しかし、俳句と短歌の違いは何ですかと問われたら、いったいどう答えればよいでしょうか? 字数が違う、季語があるのとないなどはもちろん答えとしては正し... -

『縦糸横糸』河合隼雄
生きるという縦糸に、時代という横糸。 心理学者として知られる著者が、産経新聞に連載してきたコラムをまとめた一冊です。時代のなかに生きるということに対する、具体的な72の提言が掲載されています。タイトルからキーワードを拾っていくとさまざまな問... -

『他者が他者であること』宮城谷昌光
「他者」があるから、「自分」がある。 中国の歴史小説を書き続けている宮城谷昌光のエッセイ集です。本書の特徴は何といってもその多彩な内容が凝縮されている点でしょう。「Ⅰ 湖北だより」「Ⅱ 中国古代の構図」「Ⅲ カメラ」「Ⅳ 他者が他者であること」の... -

『10代のための古典名句名言』佐藤文隆 / 高橋義人
思考が深い人は、座右の銘をもっている。 「大人になるとはどういうことか?」という問いに対するアドバイスとして、本書は書かれています。特に10代の人生においては、さまざまな疑問や不安そして悩みは尽きないものです。そんなとき古典の名句や名言が何... -

『桜前線開架宣言 Born after 1970 現代短歌日本代表』山田航 編著
個性あふれる歌人が集まったとき、それを人は「代表」と呼ぶ。 何とも目を惹く装幀の本です。タイトルも変わっています。「桜前線開花」ではなく「桜前線開架」です。本書は現代短歌のアンソロジー(詞華集)で、しかも1970年以降に生まれた歌人だけを取り... -

『青春とは、心の若さである。』サムエル・ウルマン(作山宗久 訳)
心の在り様ひとつで、あなたは青春真っ只中! 「青春」と聞けば、通常は10代や20代の若く瑞々しい感情をもった時期を思い浮かべます。誰しもこのように意識が働くものです。しかし、本書のタイトルは「青春とは」に対して、「心の若さ」と断言しています。... -

『釈迦に説法』玄侑宗久
あなたの生き方・考え方、凝り固まっていませんか? 芥川賞作家として知られる著者の初めてのエッセイ集です。著者は臨済宗妙心寺派の僧侶でもあり、本書は小説家兼僧侶の持ち味がいかんなく発揮された一冊です。心地よい文章と、生や死についてやさしく説... -

『ゆうきとものクロースアップ・マジック』カズ・カタヤマ
彼の演じるマジックは、こころの奥底のわずかな水たまりにつくられるやさしくも忘れがたい波紋のようだ。 子どものころ、マジシャン(手品師)に憧れた経験はないでしょうか? 私が忘れられないのは町内会で見せられたロープマジックです。ハサミでチョキ... -

『新人生論ノート』木田元
ノートを二つ持つといい。まっさらのノートと、この『新人生論ノート』だ。 昭和初期の哲学者・三木清に『人生論ノート』という著作があります。本書はこの『人生論ノート』と直接の関連はないが、同じく哲学者の著者がその構成を参考にして書いた現代版の... -

『うた合わせ 北村薫の百人一首』北村薫
短歌はたった三十一音です。でも優れた鑑賞により、その歌の世界は何倍にも何十倍にも膨らんで、われわれの前に現れるのです。 「歌合(うたあわせ)」とは、歌人を左右二組に分け、詠んだ歌を一番ずつ並べて優劣を競い合う文芸遊戯のことです。主に平安時... -

『「あなた」という商品を高く売る方法 ― キャリア戦略をマーケティングから考える』永井孝尚
自分の価値は、もうひとりの客観的な自分が見つけてくれる。 自分の価値とはいったい何だろう。日々暮らしていると、このような疑問がふっと湧いてくることがあります。しかしその答えを求めようとすると、他者と比較してとりたててずば抜けたものがないと... -

『ことばおてだまジャグリング』山田航
跳ねる、弾む、転がる・・・。ボールじゃなくて、言葉も。 言葉遊びはどうしてこんなに面白いのでしょう。 もちろん、言葉遊びといってもさまざまです。回文、早口言葉、アナグラム、しりとり、折句などなど。 本書は全12章にわたり、縦横無尽に言葉遊びの...