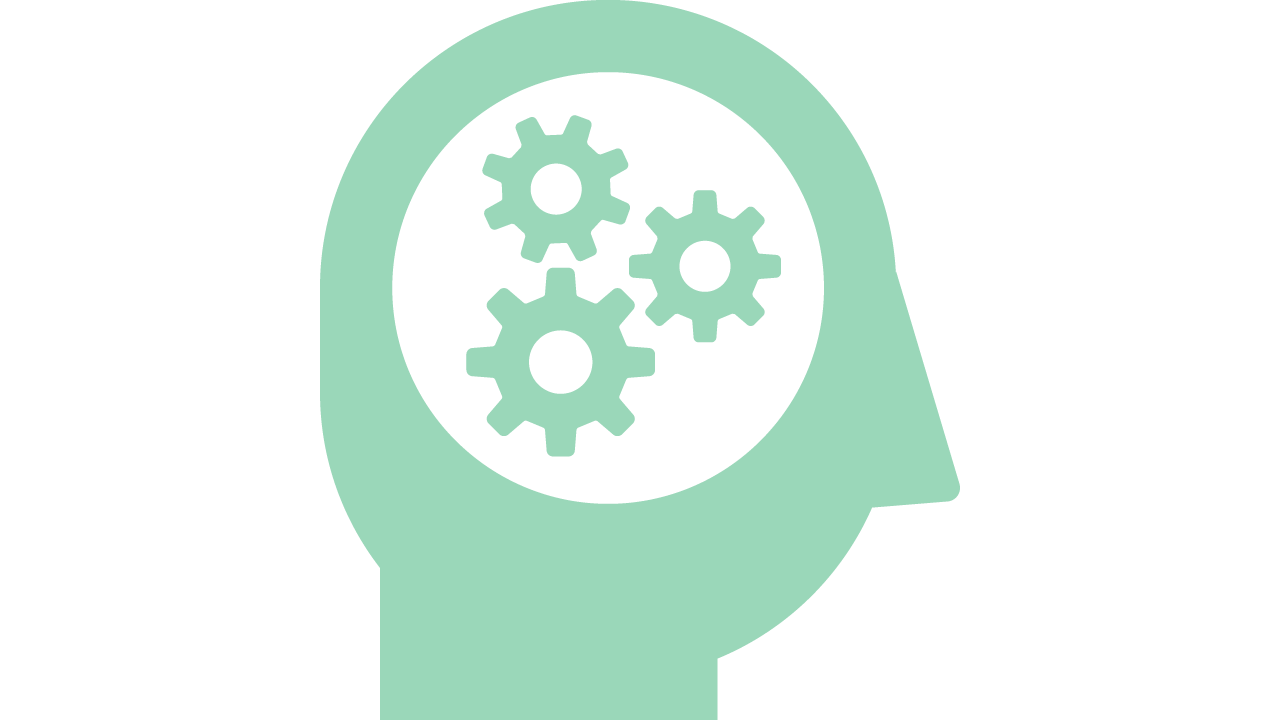「答え」よりも「問う」こと
哲学への入口として書かれる本には、哲学者の思考の断片をリスト形式や歴史形式で紹介されているものが多いのですが、本書は少し違います。もちろん哲学の歴史全体に触れてはいるのですが、それを網羅することに重点が置かれているのではなく、むしろ考えるとはどういうことかに焦点が当てられています。そこが本書の特徴であり、深く考えながら、そしてなるほどと相槌を打ちながら読み進めることができるのです。
ここで展開されているのはただの「知識」ではなく、まさしく「教養」といえるでしょう。ただ単にキーワードを哲学用語を覚えることが目的ではなく、そもそも哲学とは何かを問うています。そしてそれぞれの哲学者の思考がどういう過程ででてきたのか、あるいはどのような環境や歴史的背景で生まれたのかが語られ、非常に興味深い一冊となっています。哲学入門といっていい一冊ですが内容はとても深く、何度も読み返したい一冊です。
哲学における議論の目的は”答え”を出すことではありません。
これは非常に大切なことで、哲学においては、”問い”を出すことのほうが重要なのです。自分自身が今まで正しいと思っていたことが、はたして本当に正しいのかどうかを疑う。それがあって、初めて”問い”を出すことができます。
哲学は、人生に悩んだときに非常に身近になる学問だと思いますが、つい答えを求めてしまいがちです。しかし哲学において大切なのは「問い」だと著者はいいます。「なぜ」を繰り返すことが、哲学にとって重要なことなのです。
一般によくありがちな「哲学は役に立つのか」という問いにも、次のように答えています。
“何かのため”という手段としての知識を獲得するのではなく、”何かのため”そのものを問うのが哲学であり、目的そのものを問うのだから、それが何かの役に立つことはないという話になるのです。
それでは何のために哲学を学ぶのか? その答えはおそらく”役に立つ”ということの次元をどのように設定するかによって変わってくるのではないかと思います。
哲学は一般にいう実践的な役立ち方をするものではないのかもしれません。しかし、哲学の特徴である「特定の分野にとらわれず自由である部分」が、広い視点からの提言をなすには必要で、そこが哲学の可能性であると著者は述べています。
本書は、このように哲学とは何か、どう役に立つのかといったことを改めて考えるきっかけを与えてくれます。
もちろん本書は、哲学そのものだけでなく、哲学者を取り上げそれぞれの哲学のキーとなる部分が丁寧に説明されています。ソクラテス、プラトン、アリストテレスの古代哲学から、カント、ヘーゲル、ニーチェ、マルクス、そしてサルトル、レヴィ・ストロースの近代哲学・現代哲学に至るまで幅広く、しかも要所が取り上げられています。これら哲学者の思考がわかりやすく解説されています。
哲学を学びたい、哲学って何だろうという方にはぜひおすすめの一冊です。